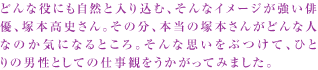
塚本さんが演じると、いつも驚くほど自然にどんな役でもスッと入りこむイメージがあります。今回、演じた琉球王国の王府の役人という役どころも“自然である”ことを意識したのですか?
塚本さん 「どの役を演じるときでも、与えられた役にそのままなりきるのではなく、自分がこの立場だったらどう動くだろうと、僕なりの解釈を入れて演じています。例えば、『テンペスト』のような歴史物語であれば、この時代の若い役人はこんな思いで政治を司っていたんじゃないかということを考えたり。今回は政治家としての手腕や頭の良さよりも、琉球という国を良くするため親身になって街の人たちの声に耳を傾けるような人間性を重視して演じました」
台本を読み込んで解釈するのですか?
塚本さん 「いえ、台本だけということはほとんどないです。現場に行って、周りの役者や監督と空気感を合わせつつ、そこで感じたインスピレーションをどんどん具現化していく感じですね」
今回の舞台は沖縄ですが、印象的だったことは?
塚本さん 「撮影許可がなかなか下りないと言われている首里城で撮影ができたことは身の引き締まる思いでした。実際にここで国のために働いていた人がいたんだと思うと、感慨深いものがありましたよ」
最初の質問に戻りますが、役者だから当たり前だとしても、塚本高史という役者はあまりにいろいろな役を自然に演じますよね。
塚本さん 「どんな役でも、絶対、自分の中に何かひとつは重なる部分があるんですよ。その部分を大きく表現することが僕のやり方で。例えば、時代劇も現代顔の人間がかつらをかぶって昔の言葉を話しているだけじゃつまらないし、見ている人も感情移入しないじゃないですか。だったら、現代の自分が共感できる部分を大きく見せて、リアリティを出すほうが自分も視聴者もすんなり入れると思うし。そういうスタンスで演じています」
そのスタンスに辿り着くまで紆余曲折ありましたか?
塚本さん 「それがまったくないんですよね。だから、役者として苦労してないほうかもしれません。親に事務所に入れられて、ただ、目立てればいいやと軽い気持ちでやって、マネージャーに言われて受けたオーディションに受かって役をもらう…なんて状況でしたから。芝居がどうしてもやりたくて、という感じではなかったんです」
それでは、なぜ15年も役者を続けられたのでしょう。
塚本さん 「17歳の時『バトル・ロワイアル』で深作欣二 監督に出会って、言われたから芝居をしている、という気持ちで役者をやっていたら周りに負けてしまうな、と思って“なんとなく演じている”から本腰を入れようと。そこから宮藤官九郎さんに出会って『木更津キャッツアイ』に出させてもらって。苦労をしたことがないのは出会いや作品に恵まれすぎているからかもしれませんね」
監督に出会って、言われたから芝居をしている、という気持ちで役者をやっていたら周りに負けてしまうな、と思って“なんとなく演じている”から本腰を入れようと。そこから宮藤官九郎さんに出会って『木更津キャッツアイ』に出させてもらって。苦労をしたことがないのは出会いや作品に恵まれすぎているからかもしれませんね」
本腰とは?
塚本さん 「もともと負けず嫌いなところがあるから、他の役者の中で埋もれている自分が嫌だったんです。『この役は塚本高史がやるから面白くなる』と周りに思われたい、そう気付いたこと。そして気付いてから、演じることが楽しくなったこと。この意識の変化ですかね」
塚本さんは今年で30歳を迎えますが、20代を振り返って、新たな意識の変化はありましたか?
塚本さん 「それを言うと今ですね。ドラマ『ランナウェイ』で市原隼人という役者に出会って考え方に変化が訪れた。僕は撮影中に“本番”と言われればONになって“カット”と言われればOFFになる。つまり撮影中だけ本気になるタイプだったんですけど、隼人はずっと本気で突っ走っている。そんな姿を見て、役者として自分も影響されたんですよ。プライベートの時間でも役のことを考えてしまう。正確に言えば考えていたいほど常に頭が演じることでいっぱいだった。でも、OFFを作らなくてキツかった分、達成感もものすごかった。確かに『木更津キャッツアイ』みたいな代表作ではないけど、自分の中で新たな試みに挑戦して、それを乗り越えられるんだと再確認した作品でしたね」
塚本さんにとって仕事に求める第一条件とは何でしょうか?
塚本さん 「自分がやっていて楽しいかどうかです。確かに、仕事ってお金や生活のために働いている人が大多数なの はわかります。でも僕の場合、役者という仕事は見ている人に夢を与える職業だと思うから、役者自身が楽しんでないと周りだって見ていて楽しいはずがない。だから、僕は楽しんで今の仕事をしています。ただ、それはどんな仕事でも同じだと思うんですよね。自分が楽しんでいなければ周りにも伝わるし、いい結果が残せるとは思えない。芸能界だってそうですよ。楽しみもせず、なあなあでやっている人は残りませんから」
はわかります。でも僕の場合、役者という仕事は見ている人に夢を与える職業だと思うから、役者自身が楽しんでないと周りだって見ていて楽しいはずがない。だから、僕は楽しんで今の仕事をしています。ただ、それはどんな仕事でも同じだと思うんですよね。自分が楽しんでいなければ周りにも伝わるし、いい結果が残せるとは思えない。芸能界だってそうですよ。楽しみもせず、なあなあでやっている人は残りませんから」