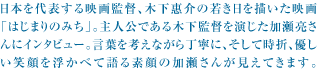
木下惠介映画の世代ではない加瀬さんが監督を演じるにあたって、どのように役を作っていったのでしょうか。
加瀬さん 「実際の木下監督に似せるのではなく、フィクションとしての木下惠介を演じました。それは最初に原監督とも確認しました。モノマネをしてもしょうがないですから。しいて言えば似せたのはもみあげぐらいですね(笑)」
今作は戦時中、木下監督が病床の母をリヤカーに乗せ、疎開先へ向かう3日間を描いた作品ですね。実際にリヤカーを引くシーンが多く印象的でしたが、何を考えながら引いていたんですか?
加瀬さん 「当時、木下監督が作った作品は、戦争 へ向かう息子を思い涙する母を描く"一人の人間"を映し出したものでした。しかし、戦時中に受け入れられるわけもなく、当局に睨まれ映画製作中止のお達しがでてしまいます。そんな内容の台本を読んで、時代は変わっても、世間では画一化された価値観が占めているのは同じなんだなと改めて思いました。僕は、単館系の映画館で多くの映画に影響されて、この世界に入ってきましたが、閉館が相次ぎ、いつの間にかそのような映画は産業として消滅しつつある。時代は違えど、映画業界を取り巻く状況や、僕自身の映画への思いを重ねて考えてしまいました。だからこそ、台本を読んだときにすごく心がうごかされました」
へ向かう息子を思い涙する母を描く"一人の人間"を映し出したものでした。しかし、戦時中に受け入れられるわけもなく、当局に睨まれ映画製作中止のお達しがでてしまいます。そんな内容の台本を読んで、時代は変わっても、世間では画一化された価値観が占めているのは同じなんだなと改めて思いました。僕は、単館系の映画館で多くの映画に影響されて、この世界に入ってきましたが、閉館が相次ぎ、いつの間にかそのような映画は産業として消滅しつつある。時代は違えど、映画業界を取り巻く状況や、僕自身の映画への思いを重ねて考えてしまいました。だからこそ、台本を読んだときにすごく心がうごかされました」
戦争という理不尽な壁のせいで、自分の作りたいものが作れない映画業界に嫌気がさして、木下監督は一旦、映画監督を辞めてしまいますよね。加瀬さん自身も役者をやめようと思われたことはありますか?
加瀬さん 「ありますよ(笑)。主人公と同じで、いろいろな制約があってやりたいことができなかったり、行きたいと思う方向へ進めなかったりすると立ち止まったりしますね。単純に自分が役者をやっていて、何かの役に立っているのかなと思うこともありますし」
でも、木下監督同様、再び戻ってきてしまう。
加瀬さん 「そうですね。周りの人も似たような経験をしていて、それでも続けている。そんな人たちに励まされることもあるし、ひとりのお客さんに励まされることもある。普段はなかなか気が付かないんですよね、自分が周りからどんなに支えられているかということが。何か困難に巻き込まれたり、追い込まれたときに初めて分かるんです」
加瀬さんが役者を続けているのは、出会う人のおかげだと。
加瀬さん 「監 督さんやスタッフさんをはじめ、役者の先輩や友人、そして映画を観てくれる人すべてがそうですね。自分が立ち止まってしまったときに、その思いをわかってくれる人がひとりいるだけで、崩れずにすむということが多々ありました。例えば、震災が起きてから、いろいろな価値観が生まれて衝突し、僕も混乱したことがありましたが、友人たちが同じ方向を向いていたことに支えられましたし。今までを振り返ってみて、何度も助けられて、その度に恵まれているなと感じますね」
督さんやスタッフさんをはじめ、役者の先輩や友人、そして映画を観てくれる人すべてがそうですね。自分が立ち止まってしまったときに、その思いをわかってくれる人がひとりいるだけで、崩れずにすむということが多々ありました。例えば、震災が起きてから、いろいろな価値観が生まれて衝突し、僕も混乱したことがありましたが、友人たちが同じ方向を向いていたことに支えられましたし。今までを振り返ってみて、何度も助けられて、その度に恵まれているなと感じますね」
劇中、木下監督の父親が『お前はなんでも、どんどん自分で決めてしまう』と嘆くセリフがありますが、ご自身に重なる部分はありますか?
加瀬さん 「そこは突かれると痛いところです(笑)。役者を始めたこともそうですが、思い立ったらすぐ行動に移してしまうタイプです。両親から面と向かって言われたことはないですが、確実にそう思っているでしょうね(笑)」